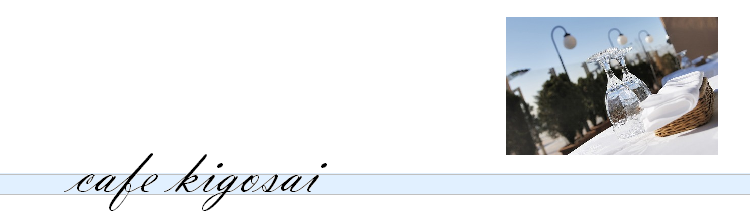くちなしの花はその限りない白さと甘い香りで、青葉の時期にその存在をアピールします。
くちなし、といわれて思い出すアメリカ映画、それはヴェネツィアに一人で休暇にやってきた、もう若いとはいえないアメリカの女性の物語。キャサリン・ヘップバーンが個性的な魅力で、この年頃のゆれる女心を見事に演じています。サンマルコ広場のカフェで、ロッサノ・ブラッツィ扮する妻子もちのイタリア男に声をかけられ、やがて数日間の恋へと発展します。好きな花は、ときかれ(くちなし)と答える彼女。ますます深まる2人の仲。やがてこれではいけないと気がつく彼女は、国にかえらなければと彼に別れを告げ、運河を航行する蒸気船ヴァポレットにとびのり駅に向います。
駅から汽車が発車していく場面、息せき切って駅に駆けつけたロッサノ・ブラッツィを残し、彼女を乗せた汽車が遠ざかる。窓から身を乗り出した彼女は、胸いっぱいの思いで駅を見つめると、プラットフォームを走る彼を見つける。速度を増す汽車に、もう間に合わないと諦めた彼が持っていた箱からとり出して彼女に向ってかざしたのは、純白のくちなしの花でした。それがわかった彼女が、手を大きく振る姿でこの映画は終わります。
一重や八重のくちなしの花。その花が美しいのは長くても一日、すぐに茶色くなってしまいます。所詮、旅での行きずりの恋も同じ。でも真白なくちなしの花は、彼女の心に長く残ることでしょう。この「旅情」(Summer time in Venice)という映画にくちなしを選んだのは、脚本も担当したデヴィッド・リーン監督にちがいないと思っています。「アラビアのロレンス」、「ドクトルジバゴ」、「戦場にかける橋」、「逢引」ーー 巨匠といわれるゆえんです。
くちなしの花で思い出すことがあります。旧知の染色作家のご夫婦の紬の展覧会でのこと、私はある紬の前で長い時間たたずんでいました。それは、黄色い線が何本も入り、その繊細な黄色が層となった紬の訪問着でした。黄の色合いが深いだけでく、その色の度合いが微妙に異なりさまざまな光を発していました。
「くちなしの実からとった染料を使うと着物に虫がつかないんだよ」染色作家のそのことばは、子どもの頃庭でくちなしの花を切ろうとして、大きな虫をみつけ飛び上がったことのある私には意外でした。くちなしの実で染めたその紬は、なけなしの財布をはたいて手に入れた、自分で買った初めてのきものとなりました。
実を結ぶと、くちなしの役目は違う方向に展開していきます。染められたものには虫がつかないという特徴を生かした染色のほか、きんとんの色をつけるのにも用いられるように食品にも、また漢方薬にもつかわれます。デビッド・リーン監督は花が終わった後、実になってさまざまな場面で役立つくちなしの事を知っていたでしょうか。
キャサリーン・ヘップバーンはその後多くの映画に出演し、天寿を全うしたそうです。(光加)