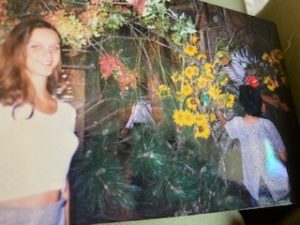小さな庭の付いた家に引っ越した時、母は背の丈ほどの紅梅を植えさせました。
小さな庭の付いた家に引っ越した時、母は背の丈ほどの紅梅を植えさせました。
塀の向こう側は隣家の台所に面しているらしく、小窓が開いている時は洗い物の音がこちらに聞こえてきました。塀の近くに植えた梅の枝が塀を越したら、隣の台所からも枝先につく花が見えて楽しめるだろうと思ったものです。
ところがある時その家から火が出て、延焼は免れたものの塀をとうに越していた紅梅は煙のせいか真っ黒になっていました。庭掃除をしながら「もうすぐ咲くわね、この蕾」と楽しみにしていた母が「焼けちゃったわ」とがっかりしていたのを覚えています。紅梅は切られ、そのあとに新しい木が植えられることはありませんでした。
お稽古の折、ごくたまに花屋さんから紅梅が届けられることがあります。お願いしている花屋さんは、私の属する流派の本部に代々花材を収めている花屋さんです。私も親先生からの付き合いもあり、時たま珍しいものが一束だけはいっていたりするのです。
紅梅の枝をいけることになった生徒さんには「いまどき都会の真ん中で紅梅をいけるのは贅沢よ」と、独特の枝ぶりや花の付き具合、幹の形をよく観察していけてねとアドバイスをします。
紅梅の枝をのこぎりで切ると、髄がピンク色になっているものが多く見られます。稽古の後、紅梅の太い枝を切った残りが他の枝とともにバケツに捨てられているのを見かけると、しおれて黒ずんでいくのが比較的早い花そのものより、髄の色で紅梅を確認することができます。
白梅は万葉集に一番多く登場する植物とされています。一方紅梅はもっと後になってから文献に登場し、「東風ふかばにほいおこせよ梅の花・・・」と菅原道真が詠んだ梅は、居宅を「紅梅殿」と呼んだところから紅梅ではないかと言われています。
源氏物語の第四十三帖は「紅梅」。紅梅大納言の一家の話で、中の記述にも梅の一枝を折りて・・・というところがありますのでこれも紅梅なのでしょうか。
紅梅には、年末や新年に咲く(寒紅梅)、その名の通り他の紅梅より大きな花を咲かせる(大盃)、中輪の(東雲)などがあります。(佐橋紅)や(紅千鳥)とはどんな紅梅なのでしょう。
今では園芸種も多くみられ、紅色の花で八重咲の野梅系は(八重寒紅)、紅梅のようだけれどよく見れば紅色のほかに白や絞りの花も付いている三月頃に咲く梅は(思いのまま)。このどこか艶っぽい響きの名は、白、紅、白に紅の斑入りなど、人が梅を思い浮かべた時のまさに思いのままの色に梅が答えてくれると言っているのでしょうか。
寒さが少しやわらいだら、今年は梅林をゆっくり歩いてみたいと思います。(光加)